電圧とはどんなもの?
電圧ってどんなものか知っていますか?

乾電池のこと?
そうですね!乾電池やコンセントが持っている力を「電圧」と呼んでいます。
乾電池をよく見てみると、単位が書いてあります。

乾電池に1.5Vって書いてある!
それです!乾電池などに書いてある〔V〕が電圧の単位で、ボルトと読みます。
このVの大きさが大きいほど、電流を流す力が大きいんです!

電圧は電流を流す力のことなんだね!
ちなみに乾電池は大きさに関わらず、1.5Vの起電力(電圧)を持っています。

ボタン電池も大きい単一電池も同じ力を持っているんだね
実はそうで、大きさの違いは電流を流す力の違いじゃなくて、どのくらい電池が長持ちするのかの違いでしかないんです。
もう少し、オマケで電圧の世界を紹介すると、家庭用コンセントの電圧は100Vになっていますが、これは、人間に間違ってかかってしまってもギリギリ死なない電圧だからなんです。なんか怖いですね。

10万ボルトでも平気なロケット団はすごいってことね
電圧の単位は〔V〕(ボルト)で、電流を流す力の大きさを表している

電流ってなんだっけ?
電流は電気の粒が流れることでしたね。忘れてしまった場合は、前の学習を見直してくださいね。↓
https://hario-science.com/current豆電球を通る前と後で電流の大きさが変わらなかったので、電気の粒自体が減っているのではなく状態が変わっていると学びましたね。

流れる粒の数は変わってなくて不思議なやつね
前回は、お風呂は熱いとたくさんエネルギーを持っているけど、冷めても水の量は同じ。つまり、電気の粒(水)の数は同じだけど、温度は変わっている(粒の状態が変わった)という説明をしました。
電圧は、「粒の高さを変える力」がどのくらいあるのかを示していると考えてください!
例えば、乾電池なら粒の高さが0Vだったものを1.5Vに上げるし、コンセントなら100Vまで上げるってことです!

電気の粒が高いほどたくさんのエネルギーを持っているんだ!
そういうことです!
乾電池は電流を作っているんですが、イメージとしては応援です。回路=コース、電気の粒=ランナーだと考えてもいいです。乾電池はランナーを応援して、たくさんのランナーを出す=電流が大きくなるイメージです。
乾電池の役割は電気の粒の高さを上げること!
乾電池の数と電圧の関係
じゃあ実際に乾電池を使って、電圧について学んでいきましょう!
乾電池は説明書きに書いてある通り1.5Vの電圧がかけられるはずです。調べてみましょう!

どうやって調べるの?
電圧を測るのは「電圧計」を使います。

電流は電流計、電圧は電圧計ってことだね
安直なネーミングで助かりますね。電圧計も電流計と同じく、電圧1つしか測ることができません。それ以上でもそれ以下でもない道具です。
さっそくそんな電圧計を使って、電圧を測ってみましょう。電圧計は回路に対して並列につないで使います。詳しい使い方は↓のページを学習してくださいね。
https://hario-science.com/ammeter-voltmeter/じゃあ、実際に試してみましょう!
電圧計は測りたい部分に並列につないで測定するから、実験装置を組み立てるとこんな感じになります。

測定すると電圧は1.20Vという結果になりました!

1.5Vじゃないの!?
なんだか騙された気持ちになりますね!!

だまされたよ!
なぜ1.5Vじゃなかったんでしょうか?
これは、今回測っている電圧が豆電球にかかる電圧で、実際は導線などにも電圧がかかっているから、乾電池は1.5Vの力で電流を送ろうとしているけど、豆電球には1.20V分しかかかっていないと考えられますね。

誤差があったことなんだね。
はい、誤差があることを知ったうえで、乾電池の数を増やして電圧の大きさを調べてみましょう!
実際に測定すると誤差がでてしまう
直列回路の場合
乾電池を2つ、3つ、4つにして直列回路を電圧を測ってみましょう。
さてどうなるでしょうか?


乾電池が多いほど明るいね!
電圧を測ってみると、表のようになりました。
| 1個 | 2個 | 3個 | 4個 |
| 1.30V | 2.60V | 3.90V | 5.00V |

だいたいだけど、比例している!
ですね!誤差は多少ありますが、乾電池の数と電圧が比例していることがわかりますね。
乾電池を直列つなぎすると電圧が大きくなることが確認できましたね。これは小学校で習ったかもしれません。
直列回路だと電圧の大きさは電池の数に比例する
並列回路の場合
今度は同じように乾電池を並列つなぎして、豆電球にかかる電圧の大きさを測りました。


乾電池が増えても明るさは変わらない!なんで!?
結果は次の表になりました。

並列回路だと電池が増えても変わらないのね
並列つなぎをした場合は、乾電池を何個にしても豆電球にかかる電圧は変わりませんでした。

だったら電池1つでいいじゃん!
そう思いますよね、なんか乾電池が無駄な気がします。
でも、この乾電池を並列つなぎにするメリットは、電池が長持ちすることにあります。
乾電池で動く道具に入る電池の数が多いほど交換する頻度が少なくて済むんです!(同じ電気を消費する場合)

電池のつなぎかたでなんでこんなに変わるの?
不思議ですね!この仕組みを不思議に考えることができればOKです!電気の世界はまだまだ奥が深いんです!
秘密は電池の役割とつなぎ方を考えれば理解することができます!さらに学習を進めて、電気の世界を解き明かしていきましょう!
https://hario-science.com/the-role-of-batteries/まとめ
電流を流すはたらきの大きさを電圧といい単位はV(ボルト)で表す
電圧のはたらきは電気の粒の高さを上げること
直列回路の電圧は電池の数に比例するが、並列回路は電池の数に関わらず同じ
.jpg)




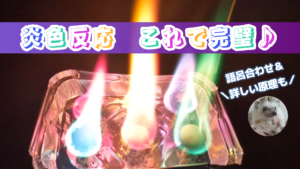

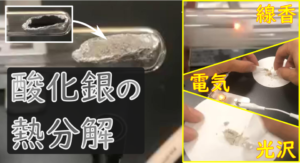

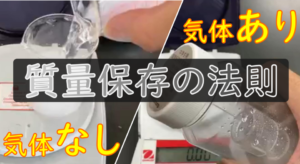
コメント