- 地震計がどのように地震を記録しているのかがわかる!
- 地震によって発生する波の種類がわかる!
-150x150.png)
うわ!地震だ〜〜
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
日本は地震が多い国だからよくあるよね〜
震度1以上::1日平均10回
震度4以上:1年間で116回
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
めちゃくちゃ多いじゃん!
でもなんで正確にわかるの?
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
それは「地震計」で記録しているからなんだ!
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
揺れてるのに記録できるの?
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
うん!そんな地震計の仕組みについて学んでいこう!
↓地震計はこんなやつ↓
-300x300.png)
-300x300.png)
それじゃあ授業スタート!
地震計ってどんなもの?
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
地震大国日本には地震計はいくつあるでしょう?
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
47都道府県あるから、470個位?
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
日本には4300個以上の地震系があるんです!
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
さすが日本!!
地震計は地震の揺れを測定するための機械です!
日本では4300個以上の地震計が各地に設置されており、気象庁や民間企業によって管理されています。
地震計は365日24時間ずっと記録を続けていて、地震によって記録される波はこのように紙に記録しています。
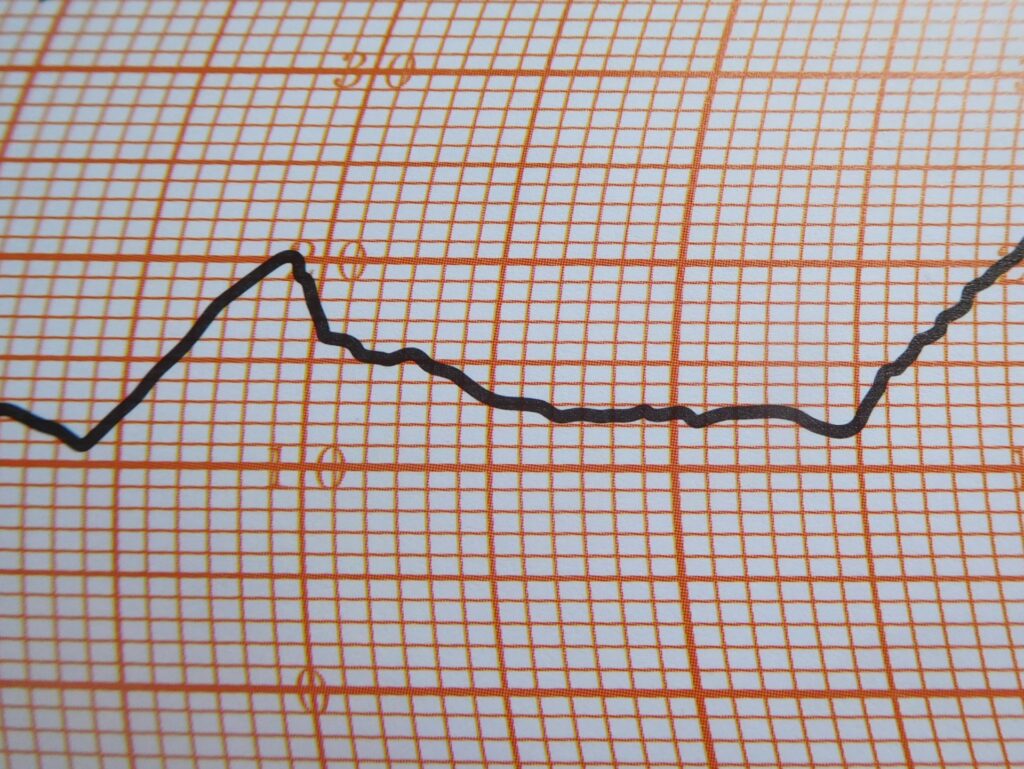
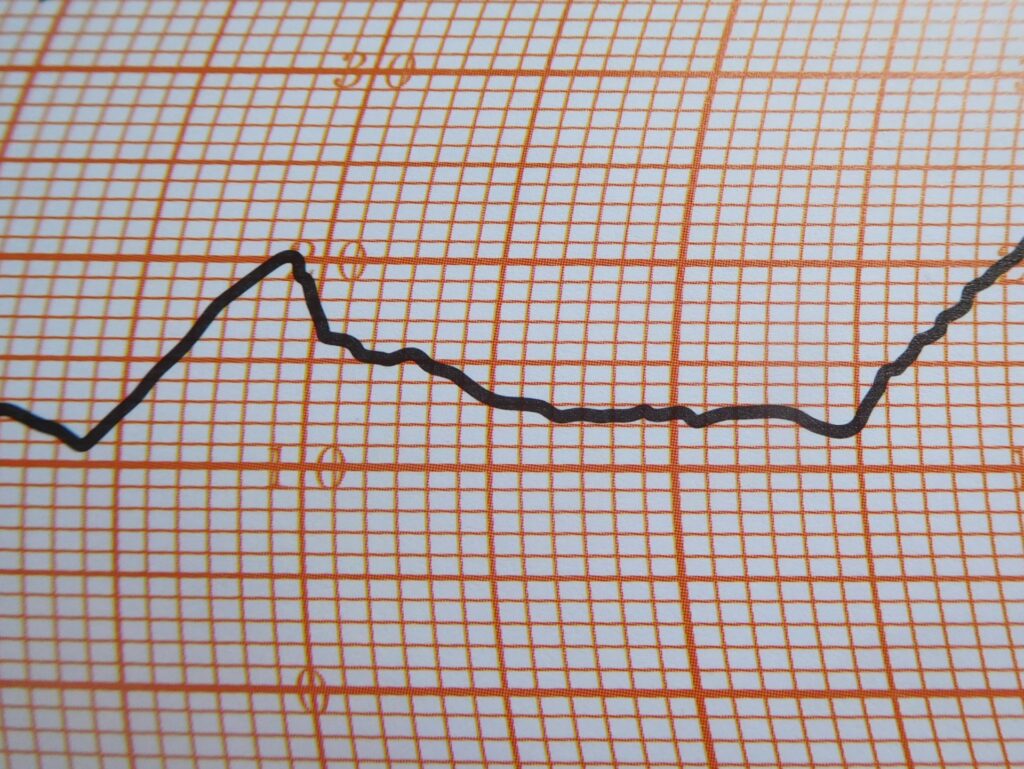
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
地震で揺れているのになんで紙に書けるの?
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
その秘密に迫っていきましょう!
地震計の仕組み
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
これが「地震計の工夫」です!
地震計はこんな仕組みで波を記録しています!
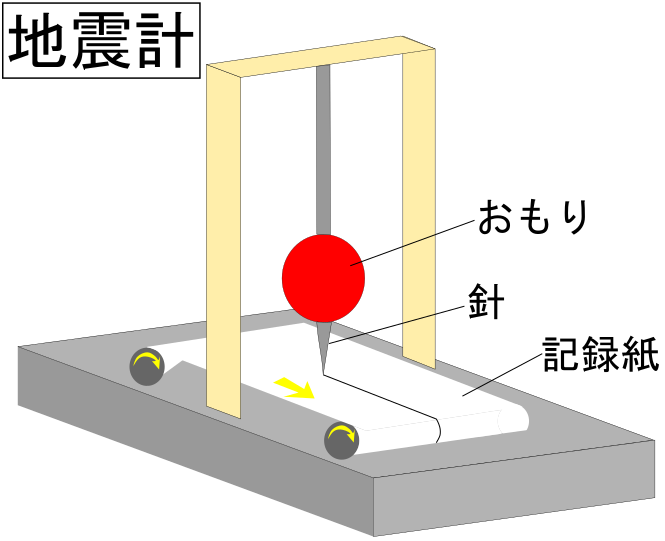
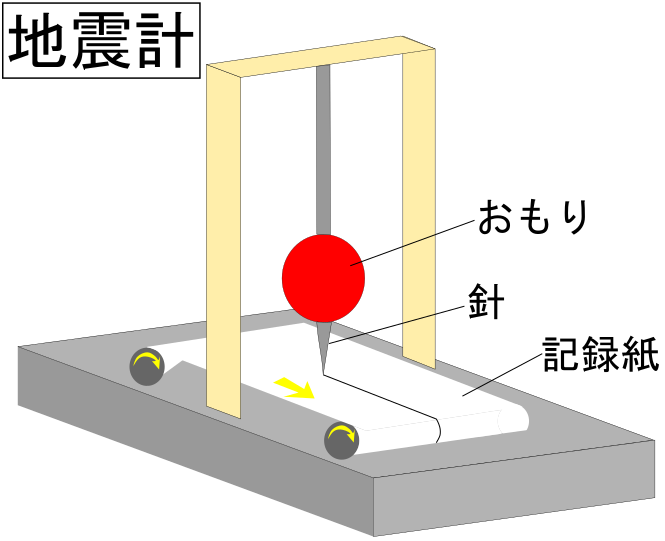
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ぼくみたいに”針”があるんだ!
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
この針で記録紙に記録しています!
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
そして重要なポイントは「おもり」です!
地震計にはおもりがついていて、地震で揺れている中でも、紙に記録できるのは、このおもりによるものです!
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
おもりがあるとなんで記録できるの?
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
その秘密を詳しく説明します!
紙に記録するということは、当たり前ですが、「紙だけをおさえてペンを動かす」必要がありますね。
両方を同じように動かしても一緒に移動するだけで、記録をすることはできません。
地震計の針はおもりにくっついているから、地震の揺れがあってもあんまり動きません。
しかし、記録紙のほうは地面にそのまま置いてあるので、地震の揺れによって動かされます。
記録は地震の揺れで動くけど、おもりについた針はそのままだから”記録紙が動く”ことで地震の揺れを記録することができています。


-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
おもりによって針は動かないけど、
地震によって記録紙は動くってこと!
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
なるほど!だから地震の揺れの中でも記録できるんだね!
地震計でわかる2種類の波
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
でもこの器具だと前後の揺れしかわからなくない?
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
よく気がついたね!
地震計は「前後」「左右」「上下」の揺れにできるように3種類あります!
今回のイラストは左右の揺れを感知するようになっていますが、記録紙の向きを3種類用意することで全方向の揺れを感知できます!
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
地震計によって記録された波はこのように記録されます!
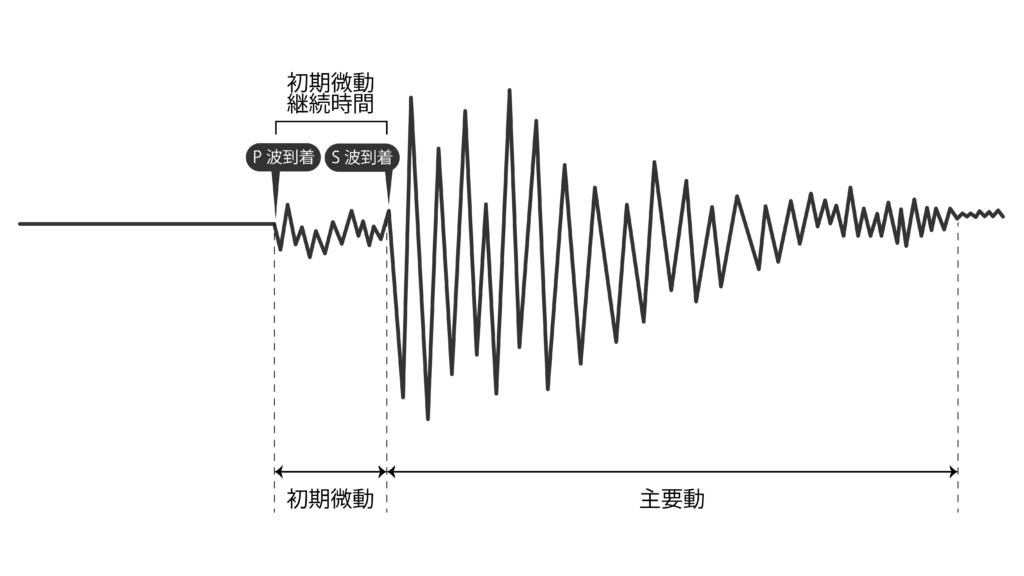
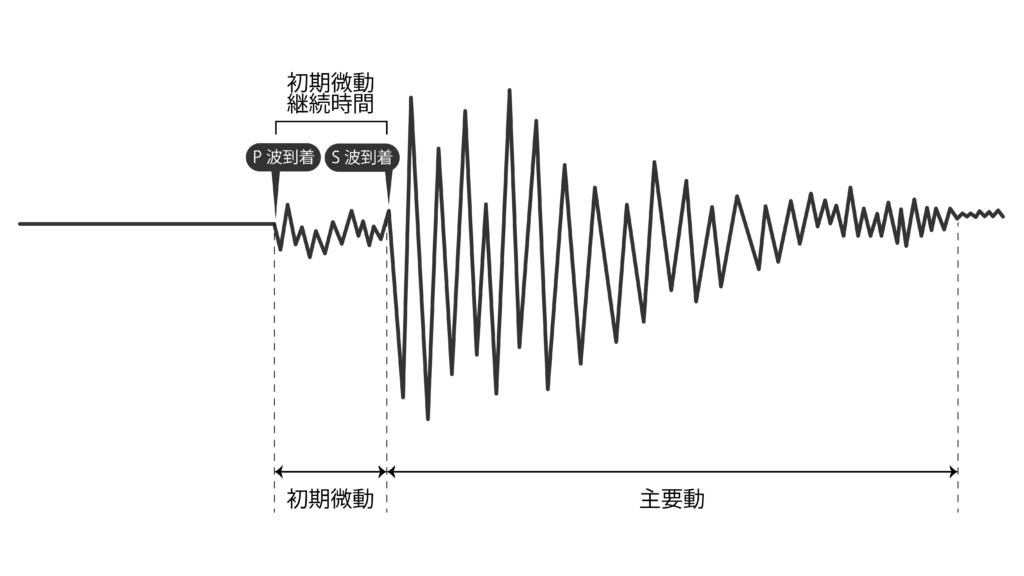
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
-1-150x150.png)
小さい揺れと大きい揺れがあるね
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
地震の波は弱い「初期微動」と強い「主要動」があります
地震の揺れはこの2種類です!
- 「初期微動」・・最初に伝わるP波によって生み出される小さな揺れ
- 「主要動」・・・後から伝わるS波によって生み出される大きな揺れ
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
P波とS波?
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
P波とS波は違う特徴があります!
P波はS波よりも速く進む波
速度は4km〜8km/sくらい
地震発生と同時にP波・S波が一緒に出発するが、P波の方が進むスピードが速いから先に揺れを伝える
P波は小さい揺れ(初期微動)を引き起こす縦波
-1024x374.png)
-1024x374.png)
S波はP波よりもゆっくり進む波
速度は3km〜6km/sくらい
地震発生と同時にP波・S波が一緒に出発するが、S波の方が進むスピードがゆっくりだから後から揺れを伝える
S波は大きい揺れ(主要動)を引き起こす横波
-1024x440.png)
-1024x440.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
P波とS波は違う特徴があります!
📡 地震計の豆知識|おもしろトピック
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
地震計の歴史や日本での使われ方もまとめておきました!
① 地震計には大きく分けて2種類ある
地震計には主に以下の2種類があります。
- 加速度型地震計: 建物の揺れの速さ(加速度)を測る。地震の震度に関係。
- 速度型地震計: 揺れの速度(地震波)を記録。震源や地震波の解析に使う。
目的に応じて使い分けられています。
② 地震計は地下にも設置されている
正確な観測のため、地下100m以上に地震計を設置することもあります。地上の騒音や振動(車・風・人の動き)を避けるためです。
こうした「地中地震計」は、特に研究用途で重要です。
③ 世界最古の「地震計」は中国にあった
紀元前132年、中国の科学者「張衡(ちょうこう)」が発明した「候風地動儀」は、世界初の地震検知器とされています。
龍の口から玉が落ちてカエルの口に入る仕組みで、揺れた方向までわかるという精巧さでした。
④ 「揺れの大きさ」と「地震の規模」は違う
地震計で測る揺れの大きさ(震度)と、地震が持つエネルギーの大きさ(マグニチュード)は別物です。
- 震度: 各地の揺れの強さ
- マグニチュード: 地震そのもののエネルギー
同じマグニチュードでも、震源の深さや場所によって震度は変わります。
⑤ 家庭や学校にも「簡易地震計」が増えている
最近では、IoT型の小型地震計が普及しており、家庭や学校にも導入されています。
地震を検知すると自動で通報したり、アラームが鳴ったりする仕組みになっています。
⑥ スマホが地震計になる時代!?
スマホに内蔵されている加速度センサーを使って、揺れを検知できるアプリ(例:MyShake)も登場しています。
将来的には世界中のスマホが地震観測ネットワークになる構想もあり、地震計の役割はもっと身近な存在になるかもしれません。
まとめ
- 地震計はおもりについた針は動かず、地震の揺れによって記録紙が動くことで記録されている
- 地震計によってできる波には「初期微動」と「主要動」がある
- 「初期微動」はP波/「主要動」はS波が伝える
今回のまとめクイズ!
-300x300.png)
-300x300.png)
次の学習も一緒に頑張ろうね!
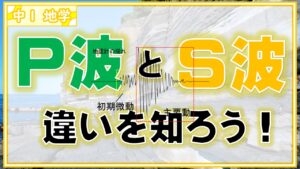
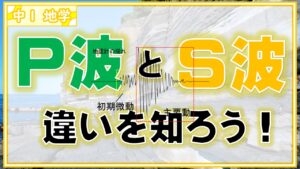


-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
今回の授業は15時間目!
- 1時間目 噴火で出てくる”火山噴出物”を紹介!
- 2時間目 マグマのねばりけで変わる火山の種類!
- 3時間目 冷える時間でかわる「火成岩」を分類しよう!
- 4時間目 6つの有色鉱物&無色鉱物を覚えよう!
- 5時間目 斑状組織&等粒状組織の違いを解説!
- 6時間目 流れる水による土砂の堆積
- 7時間目 泥岩・砂岩・れき岩は大きさで決まる!
- 8時間目 6つの堆積岩の名前を語呂合わせ!(流紋岩・安山岩)
- 9時間目 示準化石&示相化石ってどんなもの?
- 10時間目 示準化石の紹介
- 11時間目 示相化石の紹介
- 12時間目 日本が乗る4つのプレート
- 13時間目 地震で起こる4つの現象!
- 14時間目 震度とマグニチュードって何が違うの?
- 15時間目 地震計の仕組みを解説!
- 16時間目 P波とS波の揺れ方の違いってなんだろう!?
- 17時間目 地震計が揺れを感知する仕組みを解説!
- 18時間目 地震の到達時間の計算方法をわかりやすく教えます!
- 19時間目 ボーリング調査って何?
- 20時間目 柱状図から地層の傾きを考えよう!
- 21時間目 断層の種類&でき方!
.jpg)

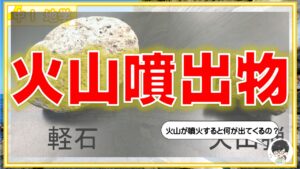


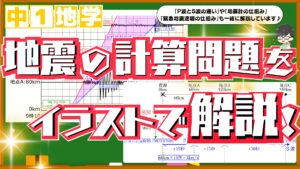
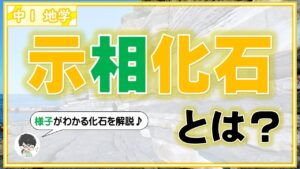

コメント